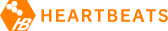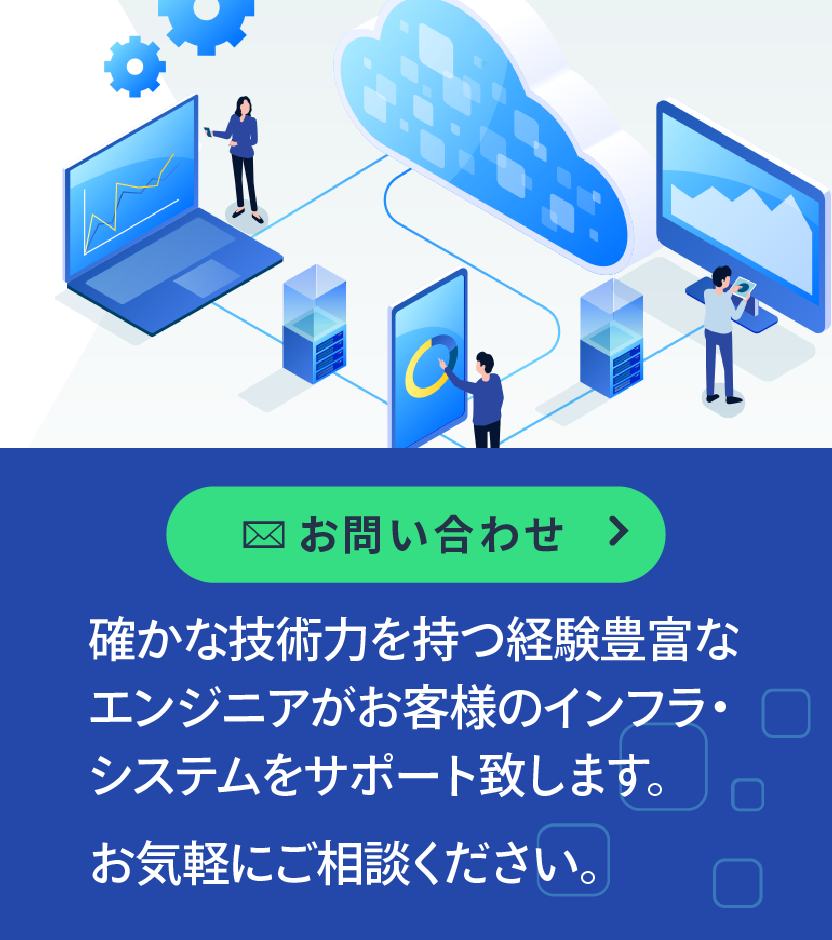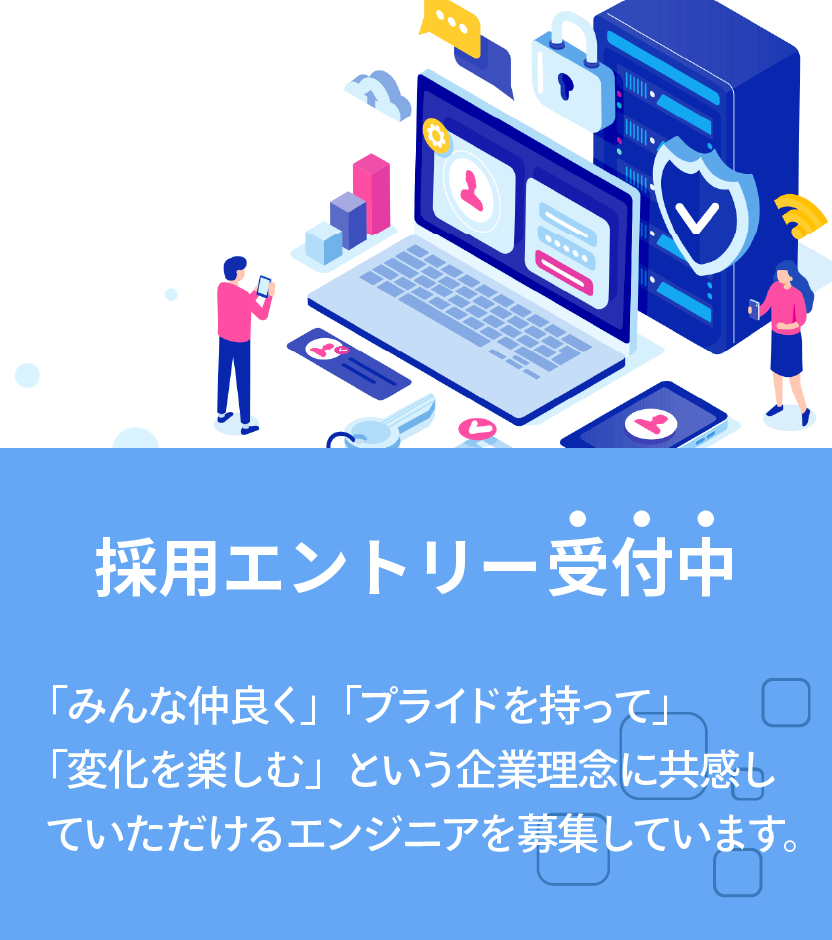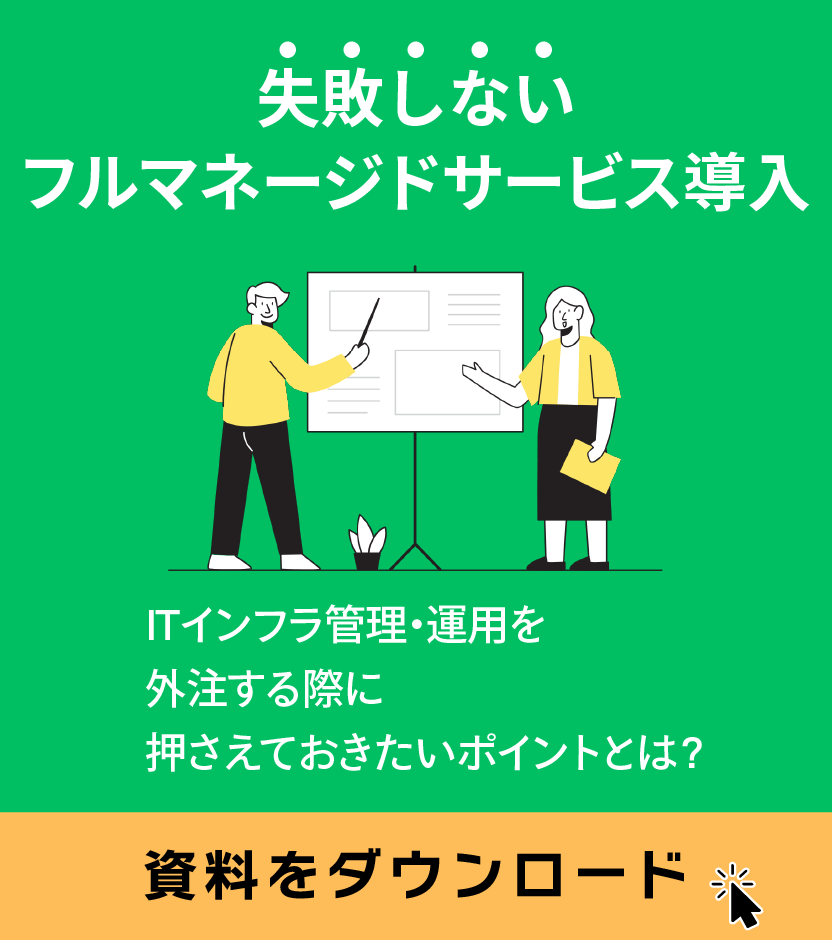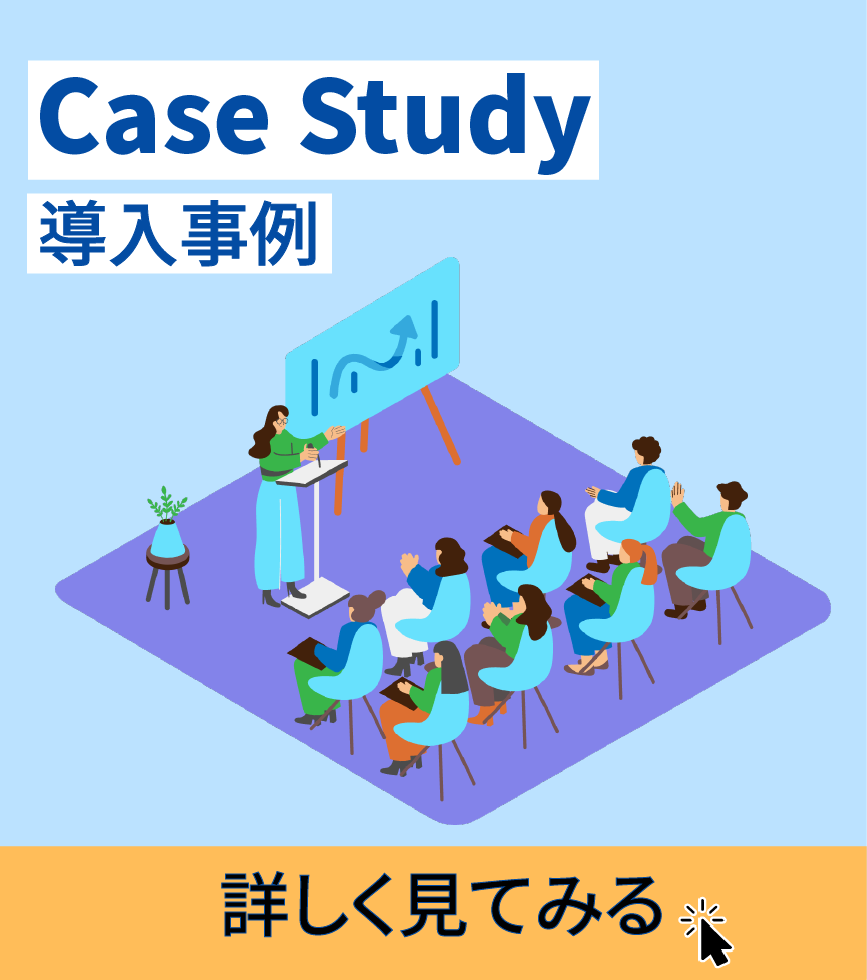こんにちは、運用チームのKimです。
システム運用において、ログファイルの肥大化はディスク容量を圧迫する一般的な課題です。この課題に対して、多くの企業でLinuxの標準ツールLogrotate を使ったログ管理が行われています。
しかし、Logrotateの運用においては、設定項目の理解不足による意図しない挙動やログの欠損などが起こることがあり、その取り扱いには細心の注意が必要です。 そこで今回は、Logrotateを安全に使いこなすための実践的な方法と注意点をまとめました。特に、運用環境での事故を防ぐための検証方法に焦点を当てて解説します。